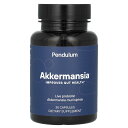和歌山の伝統の味「金山寺味噌」と発酵の魅力
12月26日に放送されたNHK Eテレ「小雪と発酵おばあちゃん」の中で紹介されたのは、和歌山県湯浅町の名産品「金山寺味噌」。この味噌は、単なる調味料に留まらず、深い歴史と文化を持ち、地域の特産物として長年愛されてきました。今回はその魅力と、金山寺味噌の秘密を探ってみましょう。
このサイトは広告を利用しています。
金山寺味噌の歴史と発酵の力
金山寺味噌は鎌倉時代に伝来し、なんと現在のお醤油が生まれるきっかけになったと言われています。その発酵過程で生じる「たまり」と呼ばれる液体が改良され、今日の醤油へと進化したのです。この味噌は、米、大豆、大麦の3種類の穀物と3種の麹を使って作られるため、風味が豊かでまろやか。特に、紀州金山寺味噌は、和歌山県で生産される瓜やなす、生姜などの新鮮な野菜と一緒に漬け込まれ、3ヶ月ほど熟成させることで完成します。
そのまま食べても美味しく、発酵食品ならではの深い旨味が感じられる金山寺味噌。実は、金山寺味噌専用の麹を購入することもでき、家庭でも作る人が増えているとか。発酵に手間がかかるものの、そのプロセスに魅力を感じる人々が多いのです。
GI認定を受けた金山寺味噌
金山寺味噌は、2017年に和歌山県内で初めて「GI(地理的表示)」認定を受けました。この認定は、世界的に有名なフランスのシャンパンやイタリアのパルマハムと同じように、特定の地域でのみ生産されることが保証された証です。紀州金山寺味噌もその対象となり、地域独自の価値を世界に発信しています。
金山寺味噌の特徴は、瓜、なす、しそ、生姜を麹と共に仕込んで発酵・熟成させた、そのまろやかで柔らかな味わいです。具体的には「具だくさん金山寺味噌」や「うす塩味金山寺味噌」、「昔ながらの味の金山寺味噌」など、バリエーション豊かな製品がラインアップされています。どれも和歌山ならではの素材と、長年受け継がれた技術によって作られています。
小雪さんも魅了された発酵文化
番組では、女優の小雪さんが発酵食品の魅力に触れながら、金山寺味噌の製造過程やその歴史を学びました。小雪さんも、その奥深い味わいに感動し、発酵がもたらす豊かな風味に触れ、発酵食品の魅力を再認識している様子でした。
金山寺味噌は、ただの調味料としてだけでなく、健康や美容にも良い影響を与える発酵食品としても注目されています。その自然な甘みと旨味は、和食だけでなく、さまざまな料理に使える万能な調味料です。
まとめ
金山寺味噌は、和歌山の地で生まれ育った歴史ある発酵食品であり、その伝統と風味は、今もなお多くの人々に愛されています。鎌倉時代から続くその歴史や、発酵の技術を次世代に伝えながら、地元の特産品として全国に広がっていっています。これからも金山寺味噌は、そのまろやかな味わいと共に、地域の誇りとして多くの人に親しまれることでしょう。