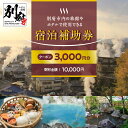『ドキュメント72時間 新春スペシャル2025』: 推し回が再び!新たな視点で深掘りする魅力的な回
2025年1月3日放送の『ドキュメント72時間 新春スペシャル』は、番組初の新春スペシャルとして、年末にランクインしなかった回の中から特に注目したいエピソードをピックアップしています。今回の番組には、山田五郎さん、鈴木おさむさん、平成ノブシコブシの徳井健太さんが登場し、それぞれが推した回を選んで紹介しています。彼らが選んだ回には、視聴者が見逃していた貴重な瞬間や感動が詰まっています。
舞台が大阪・天神橋筋にある24時間営業の格安スーパーに設定され、そこに集まる人々の生活が描かれました。この回では、日常のちょっとした瞬間を切り取ることで、スーパーという場所が単なる買い物の場以上に、さまざまなドラマや人間模様を映し出していることが伝わってきました。24時間営業のスーパーで交わる人生、大阪の繁華街・天神橋筋に位置するこの格安スーパーは、常に多くの人々が訪れる場所です。
愛知県扶桑町にあるメガネ赤札堂扶桑本店を舞台に、3日間にわたるメガネ店の風景が映し出されました。この回では、メガネをかける人々の背景や思いに焦点を当て、普段何気なく見ているメガネが、実はそれぞれの人生に深く関わっていることを改めて感じさせてくれました。
この回では、千葉市にある巨大な団地、「花見川団地」に焦点を当てています。昭和43年に建設されたこの団地には、7,000世帯が住んでおり、長年住んでいる人々と新たに引っ越してきた人々が交わる場所です。
番組では、団地内で過ごす小学生や、高齢者、外国人の住人などにインタビューを行い、それぞれの視点から団地の変化と日常を描きました。例えば、団地内の商店街では昔住んでいた人々が再び訪れ、懐かしさを感じながら買い物をする様子が描かれました。また、早朝からサッカーを楽しむ男性たちや、ボランティアで活動する新たな住民との交流を通じて、この団地がどのように変わりつつあるのかが浮き彫りになりました。
NHK『ドキュメント72時間 年末スペシャル2024』ベスト10特集
2024年の年末も、NHKの『ドキュメント72時間』は視聴者に愛され続け、待望の「年末スペシャル」が放送されました。今年の放送は、過去1年の中で最もリクエストの多かった放送回を一挙に集め、6時間半にわたる盛りだくさんの内容でお届けされました。出演者は山田五郎、鈴木おさむ、吹石一恵、そして平成ノブシコブシの徳井健太と豪華な顔ぶれが揃い、番組に登場した人々のその後の追加取材や中継もありました。
このサイトは広告を利用しています。
モツ煮込み、チャーハン、スタミナ定食、カレーなど、豊富なメニューが揃う。東京から北へ伸びる国道4号線、福島県の道沿いにある24時間営業のドライブインが舞台です。一見、懐かしさを感じさせる佇まいですが、昼夜を問わず多くの人々が訪れます。山形から東京へ荷物を運んだ帰り道に立ち寄る男性や、社会人になった息子が両親を連れて食事に来る姿も見られます。また、トラック運転手だった亡き父親との思い出を胸に訪れる人も。この場所には、それぞれの人生が交差しており、みんながどこに向かっているのかを感じさせてくれます。
舞台は日本海を横断するフェリー。新潟と小樽を結ぶ16時間の航路に3日間密着し、その魅力を探る。フェリーには、水平線を望めるデッキや、広々とした大浴場も完備。乗客は、2段ベッドや個室で過ごしながら、それぞれの時間を楽しみつつ目的地を目指す。バイクで北海道を旅する人や貨物を運ぶトラックドライバーなど、多様な乗客が集まる。現代社会の忙しさを忘れ、なぜ彼らはあえて長時間かけて船旅を選ぶのか。その理由に耳を傾け、旅の途中で交わされるさまざまな声を追いながら、船旅の魅力をひも解いていく。
肉だんごのスープや煮込み豆腐、フナの料理が並ぶ、今回の舞台は中国江西省南昌の路地裏にある貸し台所。この場所は、すぐ近くにあるがん専門の大病院に通う多くの人々に利用されています。貸し台所を使う人々のほとんどは、入院している家族を支えるためにやって来た人たちです。彼らはここで食事を作り、病室にいる患者のもとに運んでいきます。卵巣がんの娘のために野菜スープを作る母親や、父親の看病のために仕事を辞め、毎日通う青年。家族の命をつなぐ大切な料理。彼らはどんな思いで料理を作り、どんな心情でその手を動かしているのでしょうか。
パリで日本のマンガが熱狂的に受け入れられている場所、マンガ喫茶。フランス語版の日本のマンガが2万冊並ぶこの店では、時間制の料金と飲み放題のドリンクという、日本のマンガ喫茶に似たシステムで多くのフランス人が訪れています。試験を終えた大学院生や、バスで5時間もかけてやって来た姉妹など、さまざまな人々が集まります。マンガとの出会いが人生を変えたという人たちも。どんな人たちがどんな思いでマンガを読んでいるのか、深く掘り下げて紹介します。
秋田市にあるユニークなそば屋が舞台です。この店は夜10時に開店し、翌昼まで営業を続ける、昼夜逆転の営業スタイル。提供されるのは、そばだけでなく、お酒やおつまみも豊富に揃っています。店には様々な人々が訪れます。お酒を楽しんだ後にそばをシメとして注文する客や、歓楽街で接客の仕事を終えた人たち、また3月には就職や転勤を控えた人たちが別れを惜しみながら飲み明かす光景も見られます。なごり雪が舞う季節、そんな真夜中のそば屋の魅力に密着したドキュメンタリーです。
劇場のような美しい館内に、無数の本が並ぶ。舞台となるのは金沢市にある石川県立図書館。2年前に建て替えられたこの図書館は、連日多くの人々に利用されています。今回は「おしゃべりOK」というルールのもと、取材の許可を得て訪れました。ここではよくパソコン作業をする男性や、毎週訪れて料理専門書で研究を重ねるベテラン料理人の姿も見られます。図書館の独特な雰囲気に引き寄せられて来る人たちも多いようです。蔵書数は110万冊にのぼり、訪れる人々は一体どんな本を手に取り、どんな時間を過ごしているのでしょうか。
雪の札幌を走るトラックが家々を巡り、冬の生活に欠かせない灯油を届ける様子を追った3日間のドキュメンタリー。灯油配達車が家の前に停車すると、ホースを伸ばして灯油タンクやポリタンクに給油を行います。中には、片付けに夢中で暖房の灯油が切れてしまったことに気づかなかった年配のお客様や、ボイラーに灯油が不可欠な美容室を営む夫婦など、灯油を求める人々それぞれの事情が描かれます。灯油配達車に密着し、厳しい冬を乗り越えようとする人々の生活に寄り添いながら、その現実を見つめます。
今回の舞台は、24時間営業の格安ガソリンスタンド。周辺に製油所があるため、この地域には多くのガソリンスタンドが集まり、価格競争が激化しています。安さを求めて、大阪や奈良からもお客さんが訪れます。車中泊をしながら旅を続ける夫婦や、運転代行のドライバーなど、さまざまな人々がここで一息つき、それぞれの目的地へと向かっていきます。訪れた人々の声に耳を傾けながら、3日間の様子を追いました。
日本海を見渡す海岸に、約2万基とも言われるお墓が並ぶ。その舞台となるのは、鳥取県琴浦町にある「花見潟墓地」。自然に形作られたこの墓地の成り立ちは不明で、謎に包まれています。毎年お盆の時期には、多くの人々がお墓参りに訪れます。各地のお墓で迎え火が灯され、無数の灯籠がともると、夜にはこの時期にしか見ることのできない幻想的な光景が広がります。亡き家族や先祖を偲び、弔おうとする人々の姿が浮かび上がる中、海辺に広がる巨大な墓地で迎えるお盆の様子を見つめます。
舞台は温泉地、別府にある「貸間」と呼ばれる宿。宿泊料金は非常にリーズナブルで、かしこまった接客はなく、自由な雰囲気が漂っていますが、その不思議な魅力が人々を惹きつけています。もともとは湯治客に部屋を貸し始めたのがきっかけですが、今ではさまざまな人々が訪れるようになりました。3年間同じ部屋に泊まり続ける人や、出産前に旅を楽しんだという女性2人、ひとり旅を続ける男性など。また、病気の湯治のために訪れた夫婦の姿もありました。
お試し企画
・訳あり自動販売機
・キトウシ(来止臥)野営場 使える期間。6月~10月まで。
〒085-2273 北海道釧路郡釧路町昆布森村
・千葉県 老舗金物店村田屋
そして、番組のラストには松崎ナオが「川べりの家」を歌い納めるシーンがあり、視聴者に感動を与えました。今回は、その中でも特に印象深い「ベスト10」を振り返り、再放送された特集を紹介します。
「ドキュメント72時間」年末スペシャルでは、感動的なエピソードや心温まる物語が多くの視聴者に支持されました。普段の生活の中であまり触れることのない、さまざまな人々や場所の「リアル」を感じることができる本番組は、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。今年の特集を通じて、年末のひとときに感動と共に過ごすことができたのではないでしょうか。