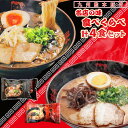愛知・豊川のメーカーが支えたパリ五輪開会式のトーチ—雨の中で消えずに燃え続けた聖火
2024年7月、パリオリンピック開会式で使用されたトーチの燃焼部を担当したのは、愛知県豊川市の「新富士バーナー」という企業でした。トーチは大きな注目を集める中、開会式当日は雨に見舞われましたが、その厳しい天候にも関わらず、聖火は消えることなく燃え続け、式典は成功を収めました。この成果に関わった「新富士バーナー」の関係者たちは、胸をなで下ろすとともに、自らの役目を果たせたことに安心感を覚えたといいます。
このサイトは広告を利用しています。
新富士バーナーの技術が支える聖火の燃焼
新富士バーナーは、コンロやランタンなどのアウトドア用品を手掛ける企業であり、その高い技術力が五輪トーチの製造にも活かされています。実は、東京2020オリンピックでも同社はトーチの燃焼部を担当しており、今回のパリ五輪でもその信頼を受け継いでいます。
パリ五輪に向けて、同社は雨や突風といった過酷な気象条件でも聖火が消えないように改良を加えました。また、昼間でも視認しやすい赤い炎を採用し、強風やランナーの動きに合わせて炎が揺らめく工夫も施しています。これらの改良により、どんな環境下でも安定した燃焼ができるようになり、開会式でもその性能が証明されました。

【ふるさと納税】【SOTO】レギュレーターストーブ ST-310セット【1265456】
- 価格: 36000 円
- 楽天で詳細を見る
雨の中での緊張の瞬間
開会式で使用されたトーチは、雨天の中でも消えることなく燃え続けましたが、その背後には何度も行われたテストと徹底した準備がありました。同社は、テレビで開会式を見守りながら、「何度もテストを重ねてきたので、うまくいく自信はあったものの、雨に加えて予想外のダンスパフォーマンスなど、想定していない動きもあったのでドキドキ、ひやひやしていました」と語っていました。
その緊張の中で、トーチはしっかりと役目を果たし、開会式の感動的な瞬間を支えました。強い風や激しい雨、さらにはランナーの動きにもしっかりと対応できるように設計されていた燃焼部は、まさに技術の結晶でした。
新富士バーナーの未来への展望
「新富士バーナー」にとって、パリ五輪での成功は大きな誇りであり、企業としての技術力が世界的に認められた瞬間でもありました。次回の五輪に向けて、さらなる技術革新を目指し、アウトドア用品をはじめとした製品開発に注力していくことでしょう。
このような一流の技術を持つ企業が、五輪という国際的な舞台で大きな役割を果たすことは、愛知県豊川市だけでなく、日本全体にとっても誇らしいことです。パリ五輪の開会式で燃え続けた聖火が象徴するように、新富士バーナーの技術は、これからも世界にその存在感を示し続けることでしょう。
まとめ
パリ五輪開会式で使用されたトーチの燃焼部を担当した新富士バーナーは、その卓越した技術で聖火を守り続けました。雨や風という厳しい条件の中でも、トーチはしっかりと燃え、開会式を成功へと導きました。開発者たちは、テレビ越しにその成功を見守りながら、技術の自信とともに胸をなで下ろしたことと思います。これからも彼らの技術は、五輪をはじめとする重要な場面で役立ち、世界中の人々に感動を与え続けることでしょう。