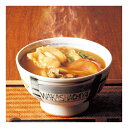のんびりとした寄り道旅!「路線バスで寄り道の旅」東急東横線沿いを巡る萬田久子さんと徳光和夫の癒しの時間
12月15日(日)15:20から放送される「路線バスで寄り道の旅」では、徳光和夫さん、田中律子さん、そしてゲストの萬田久子さんが、東急東横線沿いを巡りながらのんびりとした旅を楽しむ様子が描かれます。日々忙しいスケジュールをこなしている徳さん御一行が、今回は特別に“路線バス”を利用して、普段とはひと味違った、心ゆったりとした寄り道の旅に出発します。
東急東横線沿いを巡る旅
旅は、港区・西麻布にあるオシャレな帽子屋さんからスタート。ここで萬田久子さんのセンスが光り、徳さんと田中さんも一緒に帽子を選びながら、普段の慌ただしい日常から解放され、リラックスした時間が流れます。その後、渋谷に移動し、萬田さんが初体験となる太極拳に挑戦!運動を欠かさない彼女ですが、この新しい挑戦には徳さんも大苦戦してしまう様子。少しの汗をかきながらも、楽しく過ごすシーンにほっこりします。
思い出のレストランでフレンチを堪能
次に向かうのは、祐天寺。ここでは、萬田久子さんが思い出のレストランでフレンチを堪能します。彼女にとっても特別な場所で、美味しい料理をいただきながら、懐かしい思い出を語り合います。どんなエピソードが飛び出すのか、楽しみですね。
自由が丘での散策と、徳さんの交渉劇
そして自由が丘では、駅近くをぶらり。ここで徳さんが気になった大人気のカステラ屋さんに立ち寄ります。気になる店に対して、思わず交渉してしまう徳さんの姿に注目です。さて、カステラ屋さんとのやり取りはどんな展開になるのでしょうか?ほんわかした雰囲気の中での交渉が、視聴者を笑顔にしてくれること間違いなしです。
最後は神泉の予約困難なレストランへ
旅の締めくくりは、神泉にある「予約の取れないレストラン」で豪華なディナー。予約が取れないという名店で、どんな料理をいただけるのか、期待が膨らみます。萬田さん、徳さん、田中さんが心ゆくまで美味しい料理を堪能するシーンは、まさに旅の最後を飾る贅沢な時間です。
ふらっと寄り道の旅で心もリフレッシュ
この「路線バスで寄り道の旅」は、日々忙しく働く人々にとって、心をリフレッシュさせてくれる素敵な時間となることでしょう。普段の生活では感じられない、のんびりとした空気の中で、おすすめスポットを巡りながら繰り広げられる三人の楽しいトークや小さなハプニングに、思わず微笑んでしまいます。
12月15日(日)15:20からの放送をお見逃しなく!